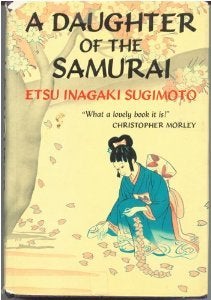第一次世界大戦後アメリカは経済的な大繁栄を迎える。
いかにもアメリカという、車、冷蔵庫、映画などはここから始まる。
しかし経済的な生活が豊かになった一方で、
モラルの低下や社会のルール無視や家庭崩壊も始まる。
アーネスト・ヘミングウェイの「日はまた昇る」は
そういう繁栄になじめず人生に挫折していく姿を描く。
村上春樹の翻訳でも有名なスコット・フィッツジェラルドの
「グレート・ギャッツビー」も同じ時代の話だ。
そういう歴史的な本とまったく同じ時代、
1925年(大正14年)に
1925年(大正14年)に
はアメリカで出版され、それらと肩を並べるベストセラーになり、
フランス、イギリス、ドイツスウェーデンなど7ヵ国で翻訳出版され
全世界的な評価を得た。これだけで凄くない?
勿論、原文は英語だ。
書いたのは歴とした日本人女性で、しかも二世でも三世でもなく
幕末に長岡藩の筆頭家老だった稲垣平助の娘ときたもんだ。
もしかすると「上を向いて歩こう」の文学版だったかもしれない。
なのにこんな世界のベストセラーが日本で出版されたのは
戦時中の1948年、見向きもされず復刻はなんと1960年。
浅学の私は本の存在すらこの本を読むまで知らなかった。
「鉞子(えつこ) 世界を魅了した「武士の娘」の生涯」内田義雄
「鉞子(えつこ) 世界を魅了した「武士の娘」の生涯」内田義雄
だから目からウロコで一気に読み終えた。
謙虚、品位、忍耐といった、大昔の日本の美徳とされていたものが
第一次世界大戦後の世界に何故どう受け止められ認められたのか、
こりゃ、面白いわい。
南北戦争(1861年~65年)と戊辰戦争(1868年~69年)
第一次世界大戦(1914年~18年)の両国、そして太平洋戦争。
この歴史の流れのアメリカ(&イギリス)と日本の関係に
最近興味があるので
今回のこの本は私にとって絶好の出合いだった。
今回のこの本は私にとって絶好の出合いだった。
人生が壮大なドラマだし今でも学ぶところが山ほどある。
こりゃ「八重の桜」どころじゃないぜ。
ただ、最終的にはそのオリジナル本「武士の娘」も読んでからと思うので
この内田本は比較文化論の教材としても優れた本なのだろうが
内容には触れないでおく。
そしてすぐアマゾンにこっちを注文した私だ。